瀬戸内海研究フォーラム in 大阪
投稿日:2024年5月8日
テーマ
大阪の地から考える瀬戸内海の将来像
| テーマ | 大阪の地から考える瀬戸内海の将来像 |
|---|---|
| 日程 | 現地開催:2024年8月28日(水) 13:00~17:45 オンデマンド開催(限定公開):2024年11月6日(水)~11月27日(水) 【重要】8月28日(水)のみ開催のお知らせ プログラム一部変更および中止について(2024年8月26日掲載) |
| 場所 (現地開催) |
高槻城公園芸術文化劇場 北館(大阪府高槻市野見町2-33) 地階 中ホール(本会場)、2階 第1・第2展示室(ポスター掲示会場) |
| 参加費 | フォーラム:無料 |
| 開催形式 | 現地参加:開会式、第1~2セッション、表彰式・閉会式 オンデマンド配信:第3~5セッション |
| 参加人数 | 現地参加:183人 オンデマンド:アクセス数554回 |
| 要旨集 | 要旨集(HP版) |
| ポスター賞結果 | 優秀賞5名 ※最優秀賞は該当者なし 入口 莉帆(香川大学) 「地域未利用資源である放置竹林を活用した竹あかりによる地域振興について~香川大学たどつまちLaboを事例として~」 宇野 早織(香川大学) 「地域連携による世代間交流に向けた取り組み~香川大学佛生山らぼプロジェクトを事例として~」 中西 美桜(大阪公立大学工業高等専門学校) 「大阪湾沿岸域の堆積物の炭素源資化能の特徴」 古木 健太郎(大阪公立大学工業高等専門学校) 「半導体式ガスセンサーを用いた堆積物のメタンフラックス測定の基礎的検討」 奥下ちなみ、和田涼花、木村蒼来(兵庫県立御影高等学校 環境科学部) 「六甲山と神戸の海のつながりを考える」 |
| チラシ | 第31回 2024年度 瀬戸内海研究フォーラムin 大阪 チラシ |
フォーラムの趣旨
大阪湾は、瀬戸内海の中で最も流域面積が大きい1 級河川である淀川が湾奥部に流入し、流域人口や流入負荷量が最も多い水域です。また、人工護岸や人工島が多く、自然海岸や藻場・干潟面積は最も少ないという特徴があります。このため、水質・水交換の観点からみると、瀬戸内海の中で最もCOD・窒素・リン濃度が高い強閉鎖性の海域となっています。加えて、大阪湾では2022 年12 月に底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定がなされ、底層溶存酸素量の改善はなお一層重要な課題です。
今回の研究フォーラムin 大阪では、“きれいで、豊かで、賑わいのある大阪湾”を実現するためには何が必要なのか、そして私たちは何をすべきなのか、という問題意識とあわせて、今や避けることができない“地球温暖化問題”が、大阪湾の将来にどのように関わっているかの観点を含めて、さまざまの立場からの講演をしていただき、大阪湾をはじめとした瀬戸内海の将来像について議論をしたいと思います。
フォーラム内容 8月28日(水)【現地開催】
司会・進行:運営委員長 駒井 幸雄
【開会式】
(1)挨拶・祝辞
瀬戸内海研究会議 理事長 松田治
瀬戸内海環境保全知事・市長会議 代表幹事 菅範昭(兵庫県環境部長)
環境省水・大気環境局 海洋環境課 海域環境管理室 海域環境対策推進官 工藤 里恵
大阪府環境農林水産部 環境政策監 土屋 俊平
(2)趣旨説明
運営委員長(瀬戸内海研究会議 副理事長) 駒井 幸雄
【基調講演】
「瀬戸内海における環境政策~きれいで豊かな海の実現に向けて~」
講演者:環境省水・大気環境局 海洋環境課 海域環境管理室 海域環境対策推進官 工藤 里恵
【第1セッション】
テーマ:大阪湾の水質・ごみ問題の現状
主 旨:総量規制等により汚濁負荷が削減されてきた結果,この数十年間に大阪湾の水質は大きく改善されました.しかし,湾奥部では赤潮や貧酸素水塊が今なお発生しており,十分に望ましい水質が回復されたとは言い難い状況にあります.また,有機汚濁の指標である化学的酸素要求量CODは当初想定されていたほどには低下せず,多くの海域で環境基準値が達成されていないばかりか,一部海域では上昇傾向さえ確認されています.さらに,海洋ごみ問題も解決には至っておらず,大量の漂流・漂着ごみによる汚染の実態把握と対策が急務となっています.本セッションでは,大阪湾の水質とごみに関する最新の話題提供を通じて,「きれいな海」の実現に向けた課題をあらためて考える機会としたい.
座長:中谷祐介(大阪大学大学院工学研究科 准教授)
(1)貧栄養化に伴う瀬戸内海のCOD上昇
藤原 建紀 京都大学 名誉教授
(2)大阪湾の貧酸素水塊:これまでとこれから
入江 政安 大阪大学大学院 教授
(3)大阪府における海洋プラスチックごみ対策について
橋田 学 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 課長
(4)大阪湾で操業する底びき網における海底ゴミの入網状況と回収効率の推定について
大美 博昭 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 海域環境グループリーダー
【第2セッション(ポスターセッション)】
テーマ:瀬戸内海及びその周縁に関する研究・地域活動報告
座 長: (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 主査 森育子
・ポスター前説明(2階第1・2展示室)
【総括・ポスター賞表彰式・閉会】
・ポスター賞の発表 運営委員(ポスターセッション座長)森育子
・来年度フォーラム運営委員長挨拶 香川大学 教授 原 直行
・閉会あいさつ 瀬戸内海研究会議 副理事長 日高 健
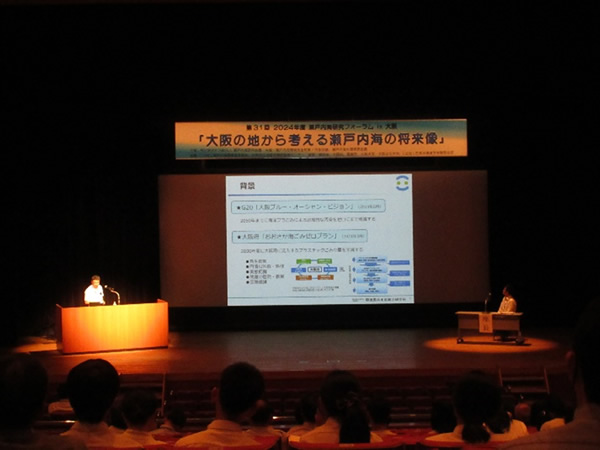
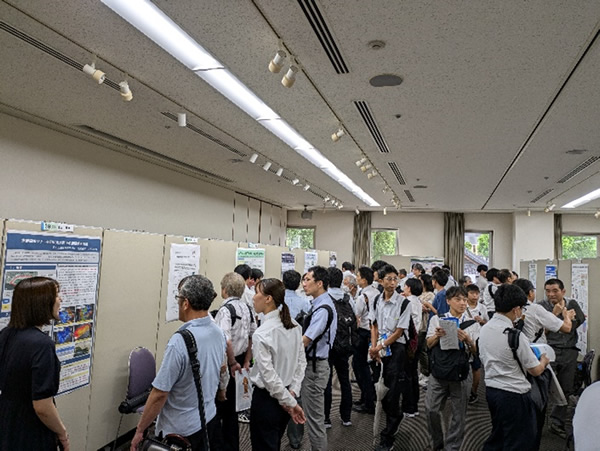
フォーラム内容 11月6日(水)~ 11月27日(水)【オンデマンド開催】
【第3セッション】
テーマ:海域特性に応じた漁業と環境改善の取組み
主 旨:大阪湾は、未だ富栄養状態にある奥部から、藻類養殖では栄養塩が不足することがある南部まで、大きな環境勾配を持つ海域です。湾内では多種多様な魚介類を対象に漁業が行われ、淀川河口ではウナギやシジミ、奥部から南部にかけてはシラスやサワラ、トリガイなどが海域の特性に応じて漁獲されています。
湾の奥部では干潟造成、中南部では藻場造成などの環境改善が行われ、新たに定着あるいは分布範囲の拡大を期待する生物種も複数確認され、また、漁業においては新たにカキ養殖や陸上養殖などの取り組みも始まっています。
このセッションでは、富栄養化した海域から貧栄養化が続く海域において、海域特性に応じた海面利用による豊かさの享受と環境改善について考えます。
座 長:中嶋 昌紀 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 理事
(1)大阪湾の水産資源の動向と新たな漁業の取り組み
安岡 法子 大阪府立環境農林水産総合研究所 研究員
秋山 諭 大阪府立環境農林水産総合研究所 主任研究員
(2)大阪湾最奥部に位置する淀川河口の漁業とブランド化の取り組み
畑中 啓吾 大阪市漁業協同組合 総務次長兼販売事業統括
(3)関西国際空港島における豊かな藻場環境の創造
大谷 優里 関西エアポート(株)技術統括部 環境・空港計画グループ マネージャー
(4)大阪湾生き物一斉調査17年間からみた海岸生物相の変化とその保全
鍋島靖信 大阪市立自然史博物館 外来研究員
【第4セッション】
テーマ:環境と漁業・食文化が調和した賑わいのある大阪湾
趣 旨:大阪湾の透明度は年々上昇しており、排水規制や下水道高度処理の普及等により、窒素やリンの値についても環境保全目標が達成されている等、大阪湾の水質は昔に比べて大幅に改善されています。しかし、大阪の海のイメージについて、大阪府民インターネットモニターアンケート結果(平成26年度)では、「昔に比べてきれいになった」と41%の人が答えている一方で、「どちらかといえば悪いイメージ」と答えた人が56%と半数を超えています。依然として、大阪湾は「近くて遠い海」なのかもしれません。しかしながら、大阪湾は、漁業生産の役割だけでなく、①自然環境を保全する機能、②国民の生命・財産を保全する機能、③交流等の場を提供する機能、及び④地域社会を形成し維持する機能等の多面的な機能を有しています。すなわち、大阪湾は、豊かであるだけでなく、「賑わい」を創出する場としても活用されています。
座 長: 矢吹 芳教 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 主幹研究員
(1)「近くて遠い大阪湾」から「親しみのある大阪湾」へ 要旨/発表資料
黒田 桂菜 大阪公立大学大学院現代システム科学研究科 准教授
(2)南泉州地域を中心とした水環境保全・創造に関する取り組み
岩井 克巳 株式会社漁師鮮度 代表取締役
(3)豊かな大阪湾をめざして ~大阪湾における令和の里海づくり~
和田 峻輔 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 総括主査
【第5セッション】
テーマ:気候変動と大阪湾・瀬戸内海 ― 生態系が受ける影響と与える影響―
趣 旨:大阪湾・瀬戸内海といった沿岸域は,陸域と隣接していることから、人々の生活の影響を受けやすい場
です。また、外洋に比べ水深が浅いことから、生物生産が活発であり、大気-水―堆積物の繋がりが強い場でもあります。
こうした中、IPCC第6次報告書によれば,地表温度は21世紀末までに1.4~5.8度上昇するとされ,気候変動が沿岸生態系に与える様々な影響が懸念されています。一方で、沿岸生態系は、気候変動を緩和する機能(ブルーカーボン機能)を持つ可能性も指摘されています。
これらを踏まえ、本セッションでは,「気候変動」と「沿岸生態系」の関係に焦点をあて,①気候変動が生態系に与える影響と,②生態系が気候変動に与える影響について考えます。
座 長:相馬 明郎 大阪公立大学大学院工学研究科 教授
(1)気候変動と栄養塩類管理が瀬戸内海の水環境に与える影響~陸域-海域統合の視点から~
東 博紀 国立環境研究所 上席主幹研究員
(2)プランクトンから見た瀬戸内海の現状と変遷 要旨/動画
西川 哲也 兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センター 上席研究員
(3)物質循環を駆動する河口干潟の炭素固定機能の動態―淀川河口を例として-
大谷 壮介 大阪公立大学工業高等専門学校 准教授
(4)堆積物-水-大気の繋がりから見た豊かな海とブルーカーボン
相馬 明郎 大阪公立大学大学院工学研究科 教授
ポスター発表募集 ※募集は終了いたしました
フォーラムでは、「大阪の地から考える瀬戸内海の将来像」をテーマとしたポスター発表の機会を設けています。学生や社会人、年齢や所属を問わず、ぜひご応募ください。ポスター発表の詳細については、上記の資料をダウンロードの上、ご確認ください。
| 申込方法 | 1)氏 名 / ふりがな 2)所属名 3)参加日[ 8/28 ・懇親会・ 8/29 ] 4)連絡先[ メールアドレス ] 5)所属先またはお住まいの都道府県名 【申込先】Googleフォーム E-mailweb@seto.or.jp |
|---|---|
| 申込期限 | フォーラム:8月23日(金)まで ※定員に満たない場合は当日受付可 懇親会:8月19日(月)まで |
資料 | 募集は終了いたしました。 ・ ・ ・ |
関係機関
- 主催
- 特定非営利活動法人 瀬戸内海研究会議
- 共催
- 瀬戸内海環境保全知事・市長会議、瀬戸内海水環境研会議
- 協賛
- (公社)瀬戸内海環境保全協会、大阪湾広域臨海環境整備センター
- 後援
- 環境省、大阪府、高槻市、大阪大学、大阪公立大学、(公社)日本水環境学会関西支部
運営委員会
- 運営委員長
- 駒井 幸雄 (特非)瀬戸内海研究会議 副理事長(元大阪工業大学)
- 幹事長
- 矢吹 芳教 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 主幹研究員
- 運営委員
-
中嶋 昌紀 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 理事
森 育子 (地独)大阪府立環境農林水産総合研究所 主査
入江 政安 大阪大学大学院工学研究科 教授
中谷 祐介 大阪大学大学院工学研究科 准教授
相馬 明郎 大阪公立大学大学院工学研究科 教授
橋田 学 大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課 課長
和田 潔 高槻市市民生活環境部環境政策課 課長


