瀬戸内海研究フォーラム in 香川
投稿日:2025年9月25日
テーマ
豊かな海の実現戦略
| テーマ | 豊かな海の実現戦略 |
|---|---|
| 日程 | 2025年9月8日(月) 13:00~17:55 (懇親会 18:40~20:30) 2025年9月9日(火) 9:30~15:00 |
| 場所 | サンポートホール高松(香川県高松市サンポート2-1) (本会場)4階 第1小ホール (ポスター掲示会場)4階 第1小ホール ロビー・ホワイエ (懇親会)5階 第2小ホール |
| 参加費 | フォーラム:無料 懇親会:一般5,000円、学生2,000円 当日フォーラム会場受付で現金徴収 |
| 開催形式 | 現地参加(要事前申込) |
| 参加人数 | 315名(2日間)[1日目169名、2日目146名] |
| 要旨集 | 要旨集(HP版) |
| ポスター賞結果 |
【優秀賞3名】 ■環境分野(自然科学) 鹿島 千尋(大阪大学大学院工学研究科) 「栄養塩類増加措置が瀬戸内海の水質環境に及ぼす影響」 ■環境分野(技術開発・社会実装) 森山 遥大(香川大学) 「カメラ画像と直接採取を用いた高松市東部を流れる新川の河口堰における河川浮遊ごみの特徴解明 ■社会経済分野 石山 翔午(NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル) 「効率的なごみ回収方法の探索:小豆島の市民参加型ビーチクリーン」 |
フォーラムの趣旨
香川県では、「人と自然が共生する持続可能な豊かな海」として、「美しい海」「生物が多様な海」「交流と賑わいのある海」が相互に関係しながら同時に成り立つ海を目指すべき香川の「里海」の姿としています。この「豊かな海」の実現には、環境保全、水産業振興、観光振興の3つが同時に実現されることが重要です。
今回のフォーラムでは、環境保全に重きを置きつつも、水産業振興、観光振興についても、瀬戸内海の現状や今後の展望を含めて考察します。
豊かな海の実現、すなわち環境保全、水産業振興、観光振興の3つの同時実現のために、新たな研究や技術開発(モノ)、行政とも連携した住民の主体的な活動と連携(コト)、それらの基底をなす新しい見方、価値観について、各界で活躍する方々を講師に招いて報告してもらいます。
フォーラム内容 9月8日(月)
【開会式】
(1)挨拶・祝辞
瀬戸内海研究会議 理事長 多田 邦尚
瀬戸内海環境保全知事・市長会議代表幹事代理(兵庫県環境部次長) 上西 琴子
環境省水・大気環境局海洋環境課海域環境管理室長 西川 絢子
香川県環境森林部長 秋山 浩章
[臨席]
高松市環境局次長兼環境指導課長 鎌田 豊
(2)全体趣旨説明
運営委員長 原 直行
【基調講演】
「瀬戸内海における水環境政策~きれいで豊かな海の実現に向けて~」
環境省水・大気環境局海洋環境課海域環境管理室 室長 西川 絢子
【第1セッション】
テーマ:「豊かな海」とは?
趣 旨:瀬戸内海では栄養塩量の低下に起因する生物生産量の低下を要因として漁獲量が大きく減少し、「豊かな海」へ回帰すべく、栄養塩量の増加に関する様々な方策が考案・実施されている。一方で、地球温暖化により水温は上昇傾向であり、これまで見られなかった南方系の魚が観察されたり、資源量が明らかに増加傾向にある魚種も少なからず認められ、現在の瀬戸内海は生態系が大きく変貌する過渡期にあると思われる。魚種交代がこの後も進行するとすれば、この流れを人為的に制御することはまず不可能であるが、この現在の瀬戸内海は、果たして「豊かな海」ではなくなってしまったのだろうか?
第1セッションでは、従来魚種の漁獲量は大きく減少しているものの、増加している魚種もあることや、これらをどのように活用していくべきかを含め、現在の瀬戸内海の生態系を見定めた上で、(もちろん現況でOKとは言えないが)今の瀬戸内海をもっと肯定してもよいのでは?というセッションとしたい。
座 長:一見 和彦 香川大学 教授
(1)瀬戸内海にとって適正な栄養塩濃度とは?
森本 昭彦 愛媛大学 教授
(2)瀬戸内海における漁獲組成の変化と今後
山本 昌幸 福井県立大学 教授
(3)五感で楽しむ瀬戸内海のジオフード・ストーリー
西村 美樹 香川大学地域マネジメント研究科 協力研究員
【第2セッション(ポスターセッション)】
テーマ:瀬戸内海及びその周縁に関する研究・地域活動報告
座 長:中國 正寿 香川大学瀬戸内圏研究センター 特命助教
発表者:31名
【懇親会】
会場:第2小ホール
司会・進行:運営委員(幹事長) 一見 和彦
祝辞:香川大学 理事・副学長 秋光 和也
挨拶:次年度フォーラム運営委員長 西村 文武
瀬戸内海研究会議副理事長 日高 健
フォーラム内容 9月9日(火)
【第3セッション】
テーマ:瀬戸内海の環境保全と水産業振興に向けて
趣 旨:瀬戸内海は、我が国における漁業生産上の重要海域である。海域面積は限られているものの、水産業に果たす役割は大きい。将来にわたり、持続的に瀬戸内海から水産資源の恵みを享受できることが望ましい。その実現に向けて、同海域が潜在的に備える生物生産能力を十分に引き出すこと、また、それを発揮できる環境を整えること等が重要であろう。本セッションでは、瀬戸内海の水産業振興に資する可能性を持つ取り組みに当たっている方々から話題を提供して頂く。我が国は、漁業生産の経年的減少という課題を抱えている。この状況を踏まえて、本セッションを瀬戸内海の水産資源の持続的利用のために我々ができること、なすべきことを考える機会としたい。
座 長:山口 一岩 香川大学 教授
(1)藻場造成技術の開発とブルーカーボンへの貢献
末永 慶寛 香川大学 教授
(2)豊かな里海づくりのための網袋を用いたアサリの育成
後田 俊直 広島県立総合技術研究所保健環境センター
(3)高速増殖型珪藻の水産業利用に向けた活用術
一見 和彦 香川大学 教授
【第4セッション】
テーマ:プラスチック環境汚染に対する取り組み
趣 旨:海域におけるプラスチックごみやマイクロプラスチックによる環境汚染の問題が国内外で大きな関心を集めている。小さくなったマイクロプラスチックは回収が困難であることから、大きいサイズであるプラスチックごみを削減・回収することが重要である。海域に存在するごみの約7割は陸から発生し、それらは河川を通じて海域に流入している。つまり、問題を解決するためには、発生場所の推定、動態の解明、定量化、対策が必要である。本セッションでは、官学NPOの最近の取り組みを紹介し、プラスチック環境汚染の現状について理解し、情報共有する。そして、人間生活・社会活動だけでなく生態系を守るために必要となる対策について意見交換を行う。
座 長:石塚 正秀 香川大学 教授
(1)香川県における海ごみ対策の取組
田中 千晶 香川県環境管理課 課長補佐
(2)かがわ里海ガイドによる瀬戸内海の海洋プラスチックごみ回収の記録
森田 桂治(一社)かがわガイド協会
(3) 大阪湾流域圏における河川漂流ごみの実態調査
中谷 祐介 大阪大学 准教授
【総括・ポスター賞表彰式・閉会】
総括 運営委員長 原 直行
ポスター賞授与 理事長 多田 邦尚
次年度フォーラム案内 次年度フォーラム運営委員長 西村 文武(京都大学 教授)
閉会挨拶 副理事長 駒井 幸雄
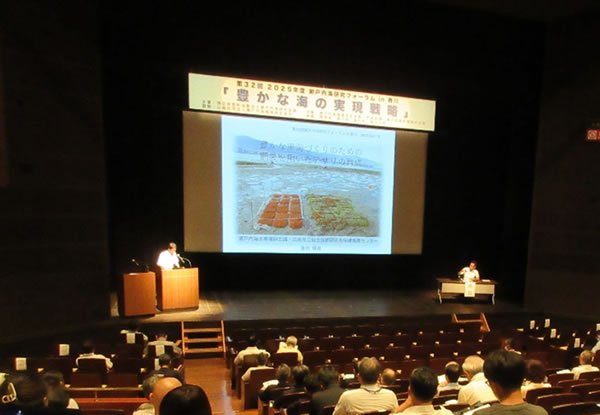

ポスター発表募集
※募集は終了いたしました
フォーラムでは、「豊かな海の実現戦略」をテーマとしたポスター発表の機会を設けています。学生や社会人、年齢や所属を問わず、ぜひご応募ください。ポスター発表の詳細については、上記の資料をダウンロードの上、ご確認ください。
| 申込方法 | 下記1)~5)の事項を明記し、いずれかの申込先に送信してください。 1)氏 名 / ふりがな 2)所属名 3)参加日[ 9/8 ・懇親会・ 9/9 ] 4)連絡先[ メールアドレス ] 5)所属先またはお住まいの都道府県名
【申込先】 |
|---|---|
| 申込期限 | フォーラム:9月3日(水)まで ※定員に満たない場合は当日受付可 懇親会:8月29日(金)まで |
| チラシ | 第32回 2025年度 瀬戸内海研究フォーラムin 香川 チラシ |
| ポスター発表関連資料 |
募集は終了いたしました。 ※応募者多数の際には先着順とさせていただき、定員になり次第、受付を終了します。 ・ ・ |
関係機関
- 主催
- 特定非営利活動法人 瀬戸内海研究会議
- 共催
- 瀬戸内海環境保全知事・市長会議、瀬戸内海水環境研会議
- 協賛
- (公社)瀬戸内海環境保全協会
- 後援
- 環境省、香川県、高松市、香川大学
運営委員会
- 運営委員長
- 原 直行 香川大学経済学部 教授
- 幹事長
- 一見 和彦 香川大学農学部 教授
- 運営委員
-
山口 一岩 香川大学農学部 教授
石塚 正秀 香川大学創造工学部 教授
中國 正寿 香川大学瀬戸内圏研究センター 特命助教
佐藤 敏幸 香川県環境森林部環境管理課長
柏山 浩史 香川県農政水産部次長兼水産課長
鎌田 豊 高松市環境局次長兼環境指導課長
千原 涼子 瀬戸内海水環境研会議(香川県環境保健研究センター)



