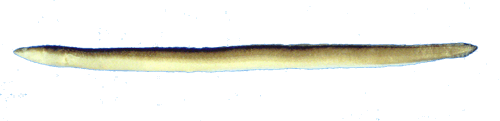
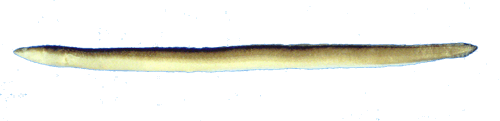 |
|
| 和名 | ウナギ |
| 網 | 硬骨魚 |
| 目 | ウナギ |
| 科 | ウナギ |
| 学名 | Anguilla japonica |
| 地方名 | アオバイ(岡山),ガニワイ(岡山),クロ(岡山、愛媛),マウオ(岡山),モドリ(岡山),ミミズウナギ(大分) |
| 分布 | 北海道以南 |
| 説明 | 淡水養殖種として重要な魚で、体は円筒形で細長く、腹鰭はありません。鱗は小さく皮の下に隠れており、体の表面はぬるぬるしています。体色は様々ですが、普通は背面が暗褐色で、腹部は白色です。全長は60㎝前後ですが、1.3mもの大ウナギも記録されています。夜行性で、小魚、甲殻類、昆虫、貝類などを食べます。川で5~15年ほど生活し、全長50㎝以上になって成熟すると、秋の台風シーズンに産卵のため海へ下ります。よく知られた魚でありながら、その産卵場は長い間謎に包まれていましたが、最近の研究で、日本の遙か南方、マリアナ諸島の西方海域あたりであることが判ってきました。約半年かけて産卵場にたどり着いた親ウナギは、産卵後、その一生を終えます。卵からかえった仔魚は黒潮に乗って日本の沿岸に運ばれて来ますが、最初は親と全く異なった姿をしており、無色透明で非常に平たく、柳の葉のような形であることから葉形仔魚(レプトケファルス幼生)と呼ばれます。あまりに特異な姿をしていることから、昔は違う魚として分類されていたほどです。その後体の形が変化し、冬から春にかけて再び川を遡る頃には円筒形のシラスウナギになります。養殖のウナギは、このシラスウナギを河口で採捕したものを育てています。種苗生産の研究も進んでおり、1999年、水産庁養殖研究所で人工授精により卵から葉形仔魚まで育てるのに成功しています。天然のものはウナギ筒や釣りなどによって漁獲されます。古くから日本人の好みにあった魚で、夏やせに効果があることはすでに万葉時代から知られていました。美味で、蒲焼き、白焼き、きも吸いなどで賞味されます。 |
(C) IDEA Co., Ltd. 1999 All Rights are reserved.